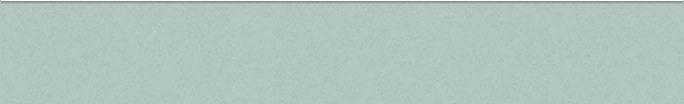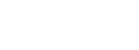研究内容
C型肝炎ウイルスの病原性発現および感染機構に関する研究
主に血液あるいは血液製剤を介してC型肝炎ウイルスは感染し、感染者は肝炎を発症します。ウイルス排除が出来なければ、10〜30年の長期に渡って持続感染し、脂肪肝や肝硬変を経て高率に肝細胞癌に至ります。HCV感染者は、全世界で約2億人、日本では200万人と推定されており、特異的な抗ウイルス剤とインターフェロン療法を併用しても、五-六割の著効率でしかなく、その副作用や耐性ウイルス出現が問題となっています。近年、様々なウイルス-培養細胞系が開発され、多くの宿主因子がHCV感染に必要であることが分かってきています。HCVの感染環は、侵入、脱殻、翻訳、ウイルス蛋白質成熟(切断)、ウイルスゲノム複製、集合、出芽、放出に分けられ、それに付随した過程で病原性が発現されます。私たちはこれら過程で関連する宿主蛋白質に焦点を当てて研究を進めています。
C型肝炎ウイルスは,、複数の受容体・補助受容体を介して細胞内に侵入し、宿主細胞内に形成される特異な膜構造物内でウイルスゲノムは複製します。必要な宿主およびウイルス蛋白質などがその内腔に濃縮されており、例えば、分子シャペロン及びコシャペロン蛋白質がこの内腔に集合し、ウイルス複製の効率化を図っています(EMBOJ.25:5015、J. Virol. 82:3480、J. Virol. 82:2631、J. Virol. 83:10427, Sci. Rep.5:16699)。ウイルス粒子の構成蛋白質であるコア蛋白質の成熟にはシグナルペプチドペプチダーゼ(SPP)と言われる膜内プロテアーゼによる切断が必要です(J. Virol. 78:6370)。この過程は感染ウイルス粒子形成に不可欠であり、コア蛋白質の細胞内局在を規定しています(J. Virol. 82:8349)。また、 コア蛋白質のみを発現するマウスは肝細胞癌、肝脂肪化、インスリン抵抗性を示します。 これまで、私たちは、ユビキチン化依存・非依存プロテアソーム分解経路によるコア蛋白質の分解が、ウイルス産生および病原性発現に関与していることを明らかにしました(J. Virol. 77:10237、J. Virol. 81:1727、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104:1661、Hepatology 52:411)。ウイルス粒子形成は、脂肪滴からVLDLへの移行過程を必要としており、VLDLに組み込まれた形で粒子がER内腔へ出芽すると考えられています(Front. Microbiol. 3:54)。蛋白質、脂質以外にもmiR122というmicroRNAを必要としており、多くの宿主因子を利用し、HCV粒子は形成されています。
ウイルスは限られた自身の蛋白質および核酸だけではウイルス粒子を複製することは出来ません。従って、感染した宿主細胞内の物質をハイジャックして、ウイルス自身を増やしていかなくてはなりません。その分子機構が分かれば、ウイルス感染および感染による病原性発現に対処する方法が見つかるはずです。また、我々はHCVと非常に近縁なウイルスの日本のウマに感染していることを突き止め、その機能的解析をし、ウイルス学的な起源を明らかにしようとしています(J. Virol. 88: 13352)。まだまだ、分からない事が多いC型肝炎ウイルスの生活環および病原性発現機構をより詳細に解析し、宿主因子との関わりを明確にしていくことが我々の研究課題です。
C型肝炎ウイルスゲノム複製を再現出来るレプリコン細胞系が開発され、更には、ウイルス感染系を再現できるJFH1株を用いた培養細胞系も樹立されたことから、インターフェロン療法以外のC型肝炎に対する治療薬開発は、大躍進しました。抗ウイルス剤が登場し、C型肝炎ウイルス排除に向けた治療法確立が整いつつ有りますが、耐性ウイルスの出現やウイルス排除後の肝がん発症への懸念、高額な医療費などの問題点を解決して行かなければなりません。私たちは、様々な既存の化合物や天然素材抽出物の中から、新たな抗C型肝炎ウイルス治療薬の候補となるような物質を探索しております(Mar Drugs, 13: 6759, 。最終的に耐性ウイルスが出現し難い、副作用がない、低額の抗ウイルス剤の開発を目標に研究しています。(琉球大、産総研、東大、星薬科大との共同研究)
B型肝炎ウイルスは、母子感染、性感染、医療行為などによる血液を介した感染によって伝播さします。特に、HBe抗原陽性妊婦の新生児に免疫グロブリンやワクチン接種の処置を行わない場合には、約80%以上がキャリアーになるといわれています。垂直感染した新生児は無症状キャリアーになりやすく、鎮静化あるいは慢性B型肝炎に移行します。血液を介して感染すると、急性肝炎となり一過性の肝障害を起こすことが多く、肝障害が長期間続いた場合(慢性化した場合)には肝癌へと進展します。B型肝炎は液性免疫による感染防御が可能となっています。1970年代に開発されたキャリアーの血漿成分から精製されたHBs粒子ワクチンから始まり、1980年代に開発された酵母による組換えワクチンが現在使われております。輸血用血液のスクリーニングと医療従事者や母子感染の恐れのある新生児に対するワクチン接種はB型肝炎ウイルス感染予防に有効ですが、依然B型肝炎ウイルス感染はなくなっておらず、より有効な新規の抗ウイルス剤開発が必要と考えられます。我々はB型肝炎ウイルスの感染初期過程やウイルスによる病原性発現機構について研究を行っています(Sci. Rep. 5:17047, J. Virol. 90: 3530, Mar. Drugs 23: 6759)。受容体の同定、ウイルス感染による細胞内微小構造の変化、ウイルス蛋白質発現機構などの解析を通して、B型肝炎ウイルスによる感染機構や病原性発現機構を理解し、B型肝炎ウイルス感染・発症をコントロールすることを目指しています。
肝炎ウイルス化合物探索に関する研究
B型肝炎ウイルスに関する研究