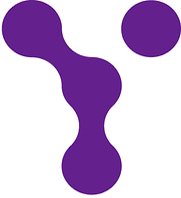心臓血管外科医を26年続けてきた。最近よく取り沙汰されるワークライフバランスという尺度で見ると、恐らく最も悪い診療科の一つである。心臓の手術は心臓を停止させて手技を施すので、循環を維持するために人工心肺装置が必要となる。その取り外しがある分、どうしても手術時間が長くなる。侵襲も大きくなる。もともと重症患者も多い。手術後も集中治療室で濃厚な術後管理を必要とすることもある。したがって病院での拘束時間も長い。数日の間、家に帰れないこともざらにある。訴訟のリスクもそれなりにある。さらに言えば、長い下積みを経ても専攻する外科医の全員が、自分である程度の数の心臓手術を執刀できる立場にまでたどり着けるわけではない。専門医資格を取得しても残念ながらその立場は保障されない。それ故に途中で断念して他科に移ったり、開業して地域医療に転向したりする例を数多く見てきた。
そのような厳しい道のりではあったが、心臓外科医を辞めようと思ったことは一度もなかった。26年の間、続けられた理由について今思い返してみると、若いころの二つのエピソードが絡んでいるように思える。一言でいうと、患者の生(せい)と同級生の死、ということになる。
患者の生のエピソードは卒後2年目の頃であった。その頃も集中治療室で術後管理に明け暮れ、ほとんど病院に泊まり込む毎日を過ごしていた。担当患者の一人は重症であった。虚血性心筋症に対して4枝の冠動脈バイパス術を施行していた。低左心機能で左室の駆出率は20%を下回っていた。苦労して呼吸循環管理を行い、術後4日目にようやく人工呼吸器から離脱し気管チューブを抜管できた。ところがその二日後、呼吸状態が悪くなり、再度挿管、人工呼吸管理が必要となった。肺炎が絡んでいるようであった。また尿量も減少傾向で肺鬱血気味でもあった。そのころは卒後2年目とはいってもそれなりの症例数を経験していたので、こうした術後経過からは、かなり見通しが厳しくなったことが分かっていた。低左心機能で一旦転ぶと、なかなか起き上がれない。透析、重症肺炎、敗血症とジリ貧となって転がり落ちていくコースが目に見えるようであった。暗澹たる気持ちで治療を続けていた。
再挿管時に使用した鎮静剤が切れてきた時に、本人の意識が戻って、筆談をさせてくれと身振りで求めてきた。看護師が紙とサインペンを渡したところ、何とか力を振り絞って一字一字書いた。そこには「イ シ ニ カ ジ リ ツ イ テ モ 生 キ タ イ」と書かれていた。「生」の一字だけが漢字で、それが妙に生々しかった。私はそれを目にして、頭をガーンと殴られたような強い衝撃を受けた。このような状況では目が覚めてもぼんやりとして、はっきりとした意思を示せないことが多い。傍から見ればほとんど死にかけているような状態でも、この患者はこれほどまでに生に執着するのかと。そして、それに対して担当医である自分は、石に噛り付くほどの覚悟で臨んでいるかと。手術の執刀は上司であったが、術後管理を主に任されていたのは自分であった。自分以外に誰がこの症例を助けるのか。生への執念にこたえて、何としても生きて返すのだ、という気持ちが湧いてきた。もちろんそれまでもベストを尽くしてきたし治療が変わったわけではない。投与薬も処置も同様である。しかし何が何でも助けるという強い気持ちだけは持つようになった。患者のその執着が生命力に通じていたのか、あるいは私の気持ちが通じたかどうかは定かではないが、数日して尿量が回復してきた。肺炎も改善し、約一週間で抜管した。10日目に一般病棟に転出し、その後はリハビリを経て自宅へ独歩退院することができた。 同級生の死というエピソードは卒後16、7年後頃のことである。大学の同級生を肺がんで失った。彼は呼吸器外科医であった。海外の留学を終え、日本の病院に就職する際の健診の胸部レ線でがんは見つかった。タバコを吸わない呼吸器外科医が肺がんに侵されるという運命の皮肉であった。
学生時代に彼とは名簿番号が近く、実習では編成によっては同じ班となった。また実家が私と同じく京都の西方にあり、時には帰りの車に便乗させてもらうこともあった。親友というほど近くはなかったが、会話の機会は多かった。大学卒業後はそれぞれ別の分野に進んだので、ほとんど会うことがなかった。共通の学会でたまたま顔を合わせた時に、少し話をする程度であった。
そんなある日、小さな同窓会が催された。彼の肺の手術からの回復を祝っての会ということを帰り道に明かされ、初めて肺がんのことを知った。それからの化学療法や放射線療法は、それぞれを専門としている同級生が担当医となって力を尽くしていた。闘病生活をしながら、彼はそれでも負担の少ない仕事をこなし、大学構内で出会うこともあった。それとなく体調を尋ねたところ、それなりに安定していると聞いて少しほっとした。
しかしその後、残念ながら容赦なくがんは進行し、彼の身体は蝕まれていった。ホスピスに入所したというのを風の便りに聞いた。見舞いに行かねばと思った。しかし何と言葉をかけてよいか分からなかった。日常の手術と周術期管理の忙しさにかまけていた。そして見舞いに行かぬままに訃報が届くこととなる。えっ、こんなに早く逝ってしまうのか、もっと早く行くべきだったという悔い。通夜には仕事を抜け出して、遅れながらも何とか焼香を上げるのが精一杯だった。
それからしばらくして同級生から、彼が生前に語っていたという次の言葉を伝え聞いた。「自分はもう自分のことだけで精一杯で、なにも患者さんのためになることはできない。みんなはできていいなぁ。」もし生前に会っていたら、自分にもこう語りかけたのではないかと思うようになった。受験戦争をくぐり抜け、医学を修めて医師となり、さらに専門領域のトレーニングを受け、海外留学も無事終えて、さあこれから患者さんのために出力全開という時に、がんのために第一線から退かざるを得なくなった。そして間もなく生命の火は消えようとする。その時の彼の無念を察するに余りある。我々には対象が何であれ、全力で打ち込むことができるのである。彼の分まで全力投球しなければならない、という想いにかられるようになった。いや「彼の分まで」などというのは烏滸がましい。彼があの世で見ているかもしれないから、せめて恥ずかしくはない仕事をせねばならぬ、という気持ちが正直なところか。
当たり前のことだが、誰も一人で生きているわけではない。仕事でもプライベートでも多くの人々と関わって生きている。そうした様々なかかわりに影響を受けて、日々の個人行動指針なるものが形作られていく。今回二つのエピソードを振り返ってみて、改めて強くそう思った。

心臓弁膜症手術風景