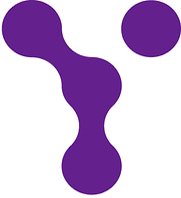研究の世界で、果たして自分は成果を残す事ができるのだろうか?研究の世界に足を踏み入れた時に、多くの人が感じる不安である。私も大学院生の時は、しばしば、迷いを感じた。研究職を得てからも、将来への漠然とした不安は残った。それでも研究者として身を立てて行く気持ちが揺らぎなく固まったのは研究生活を始めて10年あまりが経過した夏のことである。その夏、私は31歳であり、助手から講師に昇任したばかりであった。
1988年に東京大学薬学部で学位を取得した後、私は関西医科大学肝臓研究所の分子遺伝部門助手として着任した。当時のボスは喜多村直実教授(現、東京工業大学生命理工学部教授)、私が学生時代に在籍した研究室の先輩にあたる。新設講座だったので、実験室はすべての機器が新しく、機能的に設計されていて、とても実験しやすかった。
就職して最初に手がけたプロジェクトは炎症タンパク質の誘導物質の探索であった。体内に炎症などの組織破壊性病変がおこると、一群の血液タンパク質の血中濃度が上昇する。これらのタンパク質は急性期炎症タンパク(acute phase proteins)と呼ばれるが、代表的な例は臨床検査でもよく用いられるCRP(C-反応性タンパク質)である。CRPは私の学位論文でもとりあげたタンパク質であった。ただ、当時、すでに炎症タンパク質の誘導物質としてIL-6やIL-1が知られており、このプロジェクトには大きな展開も望めそうになかったので、半年ほど続けたところで実験を打ち切った。
次に手がけた仕事は企業との共同研究での肝細胞増殖因子(HGF, hepatocyte growth factor)のcDNAクローニングであった。肝臓は再生する臓器の代表的なものであり、肝再生をトリガーする液性因子の存在も古くから知られていた。HGFは肝再生因子の本体と考えられており、医薬品への応用も期待され、その実体解明には大きな注目が集まっていた。実験を始めて最初の半年は何をやってもうまくいかなかったが、最後の手段として試みた方法でようやく道が開けた。ところが、実験がうまくいって喜んだのも束の間、国内の他グループに先行されていることがわかった。共同研究先の企業からの応援も得て仕事を進め、何とか論文はpublishできたが競争には負けてしまった。ただ、幸いなことに特許は成立した。この仕事、HGFの同定にいたる一連のプロジェクトの最後の部分に関与しただけと言えば、それまでのことだった。しかし、実験の進め方については後から悔やまれることも多く、非常に苦い思いが残った。これは1989年の夏のことである。
HGFの研究はcDNAクローニングにより組換えタンパク質が生産できるようになると急速に進んだ。HGFは肝再生因子と考えられていたが、腎臓や肺の再生因子として働く可能性も報告された。いろいろな疑問も湧いて来る。HGFが細胞増殖を促進するのは肝臓の細胞に限らないのに、肝傷害時に肝臓だけで細胞増殖が促進されるのは何故だろうか?HGFの働きを制御するメカニズムはわかっていなかった。ある日のこと、古いウェスタンブロッティングの実験データを何気なく眺めていて、HGFは正常組織と傷害組織で分子としての形が違うことに気がついた。そのデータは傷害組織でのみHGFがプロテアーゼによるプロセシングを受けていることを示していた。このプロテアーゼこそ、組織傷害とHGFの作用を結びつける鍵になると考えられた。幸い、共同研究していた企業の研究員Sさんが候補となるプロテアーゼを精製していたため、すぐにクローニングにとりかかった。程なくして、当時、分子生物学では世界最強の実力をもつベンチャー企業Genentechも同じプロテアーセの研究を進めているらしいこともわかった。今度は、HGFの時のような苦い思いはしたくなかった。その1992年の夏、私は自分でも驚くほど集中して仕事を続けることができた。すでに十分な実験経験を積んでいたこともあり、頭も体もフル回転した。いくつもの実験を並行してこなしたが、操作ミスなく進めることができ、9月の声を聞く頃にはHGFの活性発現を調節するプロテアーゼの本体の解明に成功していた。
このcDNAクローニングに始まり、HGFの活性化機構の概要を明らかにするには、その後2年半を要した。Sさんをはじめ共同研究していた企業の方々、所属研究室のメンバーにはいろいろな場面で助けていただいた。幸い、この仕事は一定の評価を受けて日本生化学会の奨励賞も受賞し、研究者として何とかやって行く自信もついた。その出発点は、1992年の夏にある。
今年も夏がめぐってきて、暑い日が続いている。私は暑さに弱いので、どうしてもアクティビティーが低下気味である。そんな時、私はあの夏のことを思い出すことにしている。1992年の夏には実験に没頭するさなかに長女が生まれた。実験を中断して病院に駆けつけ、出産に立ち会ったことも鮮明な記憶として残っている。私生活の上でも、大きな転機の年であった。

(写真の説明:大学院博士課程の頃、研究室にて。左から3人目が筆者)