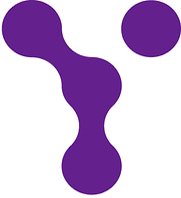陸上、例えば100メートル走が速い人は、それほど努力しなくても小学生の頃からずっと速かった。人では無いけれど、競走馬なんかも速い馬は最初から速くて、サンデーサイレンス産駒は・・・などと血統が大切にされたりする。当たり前だがDNAというか、才能が個の機能に与える影響は大きい。そんな彼ら(馬)も、トップを目指すためにはさらに血のにじむような努力をする。優れたDNA+不断の努力、しかも彼らは運を見方につけることが上手である。野球やサッカーしかり、医学、美術、音楽等々、あらゆる分野において極めた人達は同様だと思う。翻って、サイエンスはどうだろうか?当たり前だが、サイエンスを極めるにも才能は必要で、加えて様々な環境(努力)要因が要る。但しサイエンスの才能は、足が速いという才能よりも、おそらくより多くの複合的な要因を含んでいると(私は)思う。だから思わぬ人が芽を出したりする。でもどの分野にも共通して必要とされている才能が「センス」だと思う。センスは教えるのも、獲得するのも、文章で表現するのも、難しい。私の考えるセンスを敢えて書くと「大胆さと繊細さのバランス感覚」だと思う。
私が、研究の道に進もうと思ったのは大学院のD1の頃であった。ちょうどバブルがはじける少し前で、日本中、景気のいい話ばかりで皆浮かれていたように思う。様々な誘惑があった。しかし、生来の反骨的な性格故かもしれないが、以外とあっさりとサイエンスをやっていこうと思った。その割には当時はサイエンスにそれほど執着心があったわけでもなかった。良き師達に恵まれ、彼らの生き様に少し興味があったし、ちょうど少し研究成果が出てきた頃だったからだと思う。当時私は、九州大学大学院薬学研究科の植木昭和教授の下にいた。脳は何となく面白そうだ、程度の気持ちで植木研究室の門をたたいたのが最初だった。植木教授は九州大学医学部を主席(本人談)で卒業した後、薬理の貫文三郎教授の元で研鑽を積み、三十半ばにはすでに薬学部薬理学の教授になっていた。研究も、私生活も実に豪快な人であった。お酒がめっぽう強かった植木先生は、3次会4次会など当たり前で、私たち若者は束になってかかってもいつも最後には潰された。また、中洲の小料理屋を根城としておられ、那珂川(中洲の川)界隈での武勇伝には事欠かなかった。そんな私生活からは一転、研究における切れ味は抜群であり、怖かった。事実、当時の抗うつ薬の多くは植木先生によって世に送り出されたものだった。研究室に入ってすぐに、米のCosta研から帰ったばかりの助手の片岡先生と神経伝達物質放出の新しい測定方法であるreal-time monitoring系の立ち上げを行った。新しい実験方法確立の重要性はよく分かっていたつもりだが、メカニズムの解明に興味があった私は既存の方法論でのアプローチにこだわってしまい、実験系の開発はなかなか進まなかった。そんなとき、やはり中洲系であった片岡先生に、那珂川縁の小料理屋でこっぴどく絞られた。新しい実験系を開発することの重要性、既存の方法に固執する事の限界を淡々と刷り込まれた。D1の頃は、ちょうどこの新規実験系が確立出来て、いよいよこの系を使って新しい脳のメカニズムを解明する、という時期だったのである。植木先生も、新しくて良いと思われる技術・情報の導入に非常に積極的だった。私にとって幸運だったのは、大学院時代に多くの他大学・研究所のラボに新技術取得のため、里子に出させて頂いたことである。長崎大医学部薬理の丹羽教授、片岡准教授(現福岡大学教授)、上智大学生命研の熊倉教授、三菱化成生命研の工藤部長(現東京薬科大学名誉教授)、米のUCI等々。様々なラボに出入りして、多くの研究に触れ、研究者を見て、話しをした。みんな変わり者だったが輝いていた。植木先生のようになりたいとは当初から思ってはいたものの、師はあまりにも大きすぎて何となく実感が湧かなかったが、やっと少し自分の将来像が少し見えた気がした。そして、何故か根拠の無い自信を糧にして進路を決めてしまった。人は何度か自分の将来について、決断を迫られることがある。皆さんは多分、直近では大学入試だったと思うし、次は卒業後の進路を決める時だと思う。自分の将来の方向性を決める時、その人のセンスが最大限に発揮される。もちろん皆、自分の意志で決めているつもりなのだが、若者の心はどん欲で優柔不断であるので、指導教官や先輩の助言・姿、友人の言動で自分の意志とやらは如何様にも変わってしまう。さらに異性にもてたいなどと助平心を出すから、気になる異性の言動には簡単に左右されてしまう。私も人のことを言えないが、情けない。進路の選択に迷ったとき、思いっきり悩んで考えた後に、適当に決めるのが良いと思う。何それ?という感じだが、「思いっきり悩んで考えた後」というのがポイントである。実際にやってみないと、いくら悩んでも解決しない事は多いし、充分悩んだという事実が無いと、後で少し後悔する。「なんだ、選択のセンスなんて関係ないじゃん」と言われるかもしれないが、選択とか決断なんてそんなモノであり、進路や職業選択の際に自分の才能を見極めて選んでいる人は少ない(と思う)。大事なことは、決断の後だと思う。選んだ道で自分の適性を見極めるセンスがあるか、またダメなときに撤退する勇気があるか?サイエンスなんて何時でもやめる、と思って始めたこの道であるが、いまだに続けられているのは幸運なことだと思っている。
さて、研究で生きていこうと決めて、学位も無事に頂いたが、ポジションが無かった。すぐに留学しようと思ったが、最初に返事をくれた米国のラボの条件が悪すぎて、何も外国に行くだけがポスドクではないと思った。が、本当は少し自信も無かった。まだ日本ではポスドク制度(ポジション)が余り無かった頃だが、そんなとき、厚労省の国立医薬品食品衛生研究所(国立衛研)の井上和秀先生(現九州大学大学院教授)がポスドクで来ないかと声をかけて下さった。実は大学院時代、犬(Billy)と暮らしていた。捨てるわけにもいかないので、福岡から彼と一緒に飛行機に乗って上京してしまった。東京には当時、犬と一緒に住めるマンション・アパートなど殆どなかった。たまたま東京医大の渡邊助教授の一軒家が空いていたのでそこにBillyと一緒に転がり込んだのだが、その家もすぐに壊されてマンションになるとのことで、大都会で路頭に迷った。井上先生は、呆れていたと思うが、見かねて国立衛研の中に、Billyの住み処を世話してくれた。幸いビーグル犬だったので、実験しているようなふりをすれば・・・、と思ったがすぐにペットの犬だと気づかれてあちこちから苦情が出た。国民の税金で維持している研究所に・・・といったところであるが、初期の苦情の嵐を乗り越えた後、Billyは研究所中のアイドルとなり、皆の精神衛生の向上に非常に大きな貢献をしてくれたのである。研究室を主宰するようになった今、ポスドクが犬連れでラボにやってきたら一緒に受け入れられるだろうか?と今更ながら井上先生の心の大きさには感激する。とにかくポスドクをスタートすることができた。ここで、運命的な出会いがあった。アデノシン三リン酸(ATP)である。細胞内のエネルギーの通貨としてあまりにも有名なATPだが、細胞外に放出され、情報伝達物質として機能するのである。これをプリン作動性シグナルと呼ぶのだが、当時はATP受容体(P2受容体)の分子実態も全くわからず、学会等でATP刺激により・・・などと発表すると、醤油で刺激したのとどう違うのか?などという失礼なコメントも頂いた。また、それ以前に、聴衆が集まらなかった。何度か撤退しようと思った。思いとどまったのは、ポスドク2年目を迎えようとしている時に、P2受容体の1つがクローニングされたのである。運が良かった。今ではP2受容体は15種類も見つかり、殆どの組織・臓器に何らかのP2受容体が発現していることが明らかとなったし、最新版ならば薬理学の教科書にも掲載されるようになった。しかし、当時はそんなものだった。さらにこの頃、神経細胞ではなくて、その周辺に多数存在するグリア細胞のほうが、ずっと強くATP に反応することを見つけた。ATPもマイナー、グリア細胞もマイナー、こんな日陰ばっかりの研究でよいのかとも思ったが、心底ワクワクする応答であり「これは凄い」と思った。これがサイエンティストとしてのセンスで・・・などと書くつもりは毛頭無いが「大事にしよう」と強く思った。そんなことを胸に秘めながら、日本でのポスドクを終えて、英国に発つこととなった。
1996年秋に渡英して、ケンブリッジのMike Berridgeのラボにお世話になった。ボスのMikeはInsP3によるCa2+放出を発見したことで良く知られており、実際出来る男で人格も優れていた。当時、全く面識は無かったが、無謀にも自分の実験計画と業績集を添えた手紙を、推薦状も付けないでいきなり送りつけたのだった。日本人ポスドクを受け入れたことが無いMikeは、流石に不安に思ったのか、推薦者のリストを送ってきて、この中から誰かに推薦書を書いてもらうようにと依頼してきた。その中に、当時東大医学部薬理の教授になられたばかりの飯野正光教授の名前があった。飯野先生も個人的には存じ上げなかったが、無理矢理お願いして何とか推薦書を書いて頂けることになった。こうしてポスドクとして受け入れてもらったのだが、今思うと、むちゃくちゃで、礼儀知らずで、とても恥ずかしい。さすがにBillyは連れていけなかったが、とにかくスタートが切れた。当時の彼のラボには世界中から多くのポスドクが集まっていたので、Mikeと直接仕事をするのではなく、日々の研究はシニアのポスドク(小ボス)とやることになる。小ボスとは相性が悪かったし、よくけんかした。私は、ニューロンの特定部位では、極めて局所的で単寿命なCa2+放出現象(Ca2+ spark及びCa2+ puff)が起きているとの仮説を提唱し、その存在の証明と、その生理的意義の解析をしようとしていた。これは、複雑な形態を呈するニューロンの、局所レベルでの一瞬のCa2+変化が、ニューロン全体の機能及びニューロンネットワークの機能制御の基本単位である、という夢のある仮説であり、証明する前から一人興奮気味であった。当時は珍しかった高速共焦点レーザー顕微鏡がMikeのラボには何台もあって、それらを自由に使って来る日も来る日も神経細胞のCa2+ spark/puffを探していた。しかし、1年近く経っても1度たりともCa2+ spark/ puffは検出できなかった。Mikeの私に対する不信感は募り、小ボスはそれみたことかそんなモノは無いよと言わんばかりにプロジェクトの中止を提案し、さらに肝心の私自身の自信も揺らいで来た。クリスマスが近づいてきて、撤退の決断を迫られていたが、どうしても諦めきれなくて特に解決策の無いままにラボに籠もって顕微鏡を覗いていた。そんな時、なんと1回だけCa2+ puffが見えた。柄にもなくサイエンスサンタのプレゼントだと思って感謝した。それ以降も見えたり見えなかったりしたのだが、この1回のプレゼントで完全に「ある」と確信した。その後も試行錯誤が必要だったし、順風満帆とはいかなかったが、「ある」と分かったら仕事は急速に進み、順調にまとまっていった。また、日本を発つときにあたためていたグリア細胞の機能解析に高速共焦点レーザー顕微鏡を応用することを思いつき、現在のグリア-ニューロン連関の仕事のスタートを切ったのもこの頃である。サイエンティストとして道を歩み出したものの、色々と不安にはあった。ふっきれたのはこの頃だと思う。センスなのか、単なる運だったのかはまだ解らない。
学生諸君へ何かメッセージを、と思っていたが、単に自分の学生時代・ポスドク時代の恥ずかしい話を書いてきただけで終わってしまった。これを読んでいる皆さんの多くは、臨床医又は基礎医学研究者として生きていくのだと思う。進路に、適性に、人間関係に・・・と色々悩んだり不安になったりすることも多いと思う。沢山悩む事は大切だと思うが、その後は大胆というか、むしろ好き勝手にやってみると良いと思う。何とかなるものはなるし、どう頑張ってもダメなモノはどうにもならない。実際にやってみないと解らないとも多い。この原稿の最初に、どんな分野でも極めるためにはDNA+環境(努力)が大事で、特にセンスの重要性はどの分野にも共通している云々と書いた。「極める」にも色々な程度があるし、センスも多種多様である。自分のセンスを生かせる道を上手に見つけて、是非とも何かを極めて欲しいと思う。

英国のポスドク時代(1996年)。右端後ろがMike Berridge 教授、左端前が筆者。