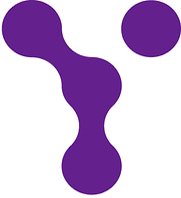私の専攻する脳神経外科では、以前は大学卒業から6年間修練し、7年目に専門医試験を受験できたが、初期臨床研修必修化以降、事実上2年間が短縮された。そのため、後期研修の間は、研究を後に回し臨床研修に特化せざるを得ない状況が生まれている。しかし、私は、「鉄は熱いうちに打て」の諺通り、若いうちに多くの臨床経験を積むことと同時に研究に従事し、科学に根ざした脳神経外科学を学ぶことが、将来重要となる論理的思考力を養う上でとても重要と考えている。最近、脳神経外科でも専門の分化がすすみ、指導体制や方法もより複雑化してきている。私は、昭和という特殊な時代に秋田大学を卒業し、東北大学で研修時代を過ごしたが、この時代は脳外科手術に顕微鏡が導入され、マイクロサージェリーによる脳卒中の外科治療が軌道にのり始めたころで、脳外科の黎明期であるともいえる。そのため、医療環境や教育体制は現在とは大きく異なっていたが、脳外科医教育の根底にあるspiritsについては不変だと感じている。そこで、昭和を知らない世代へ向けて私のレジデントならびに大学院生時代を紹介する。
私の恩師である鈴木二郎先生は、もやもや病の命名者のみならず脳動脈瘤をはじめとする脳血管障害(脳卒中)の外科治療の先駆者として本邦の脳外科の発展に大きく寄与された先生である。先生は、東北大学長町分院にあった脳疾患研究施設脳腫瘍部門の初代教授を経て東北大学脳神経外科教授に就任されたが、それ以降も、我々脳外科の臨床活動の拠点は、救急患者の受け入れ態勢事情により、大学病院ではなく東北大学長町分院に隣接した(財)広南病院であった。大学病院では、グリオーマなどの放射線治療を要する脳腫瘍を中心に診療が行われていたが、なんと2名の病棟医しかおらず、教授を含めほとんどのスタッフが広南病院でクモ膜下出血を始めとする脳卒中の外科治療と研究にあたっていた。広南病院の名の由来は、広瀬川の南という意味で、別名“長町番外地”とも呼ばれていた。陸軍幼年学校の廃材を用いた木造2階建ての建物は、およそ病院と呼べるような風貌を持ち合わせておらず、初めて訪れた人は決まって入り口正面で、当病院を探していたのを憶えている。研究室もすべてが木造で、歩くと鴬張り廊下さながらにギシギシと音がし、窓枠の隙間にはガムテープが貼られていたが、冬には粉雪が舞い込むこともまれではなかった。また、手術室はカーテンを開けると窓越しに外が見えるような普通の部屋で、2部屋のうち1部屋は解剖兼用でもう一方の大きめの部屋にベッドが2台設置されていた。医局の奥には、蚕棚と呼ばれる仮眠室が天井からぶら下がり、工事現場でよく見られる鉄製パイプの梯子を登って出入りした。そこには川の字に5人程が眠れるように布団が敷いてあった。梯子の下に脱いだサンダルの数で、空き状況がわかるが、仕事の遅い新人はいつも就寝(連日の泊まりは日常茶飯事)が後になるので、暗闇の中空き布団を探しているうちに先輩の頭や足を踏んづけ怒鳴られた。当時は医局の暖房もガスか石油ストーブで、24時間どこでも寝られるという訳ではなく、寒い冬などは、暖かい病棟のナースセンターの診察台で煌々と輝く蛍光灯のもとナースコールを子守歌につかの間、睡眠をむさぼった。
当時は脳神経外科医が少なく、県内外から多くの患者が、広南病院に搬送されて来た。クモ膜下出血の手術だけでも年間100件程度あり、総手術数は年間500~600件ぐらいだったように思う。それを、助手1名、専門医試験に向けた強化指導中の病棟チーフ1名さらに主治医3-4名で構成されるチーム2つで受け持っていた。1階が急性期、2階が慢性期病棟になっていたが、ベットの回転が速く、主治医にとっては病床が無尽蔵と思われるほど、毎日多くの患者が運ばれ、いかにも多忙を極めた。そのため、救急対応、外来と病棟診療、血管撮影などの検査手技は、先輩のものまねですぐに覚えられた。鈴木教授が、常々“Rückenmark reflex(脊髄反射)で仕事しろ”と飛ばす檄の意味がすぐにわかった。考えてから体が動くのでは遅く、自然と反射的に仕事ができるようになって初めて一人前医ということである。
また、治療方針や治療経過については助教授および教授回診で、厳しく指導(追及)されるため、前日にチームごとに徹底した回診対策がなされ、病状、問題点および方針についてのプレゼンテーションの予行演習を行った。この回診対策を通して、先輩やスタッフの考えがチーム全体に確実に伝わり、患者の状態の再確認と正確な理解ができ、とても勉強になった。しかし、教授回診は、とても一筋縄では終わらず、教授が一人の患者のベットわきに1時間以上も立ったまま、厳しくご指導いただくこともしばしばであった。しかしネーベンが失敗しても、責任を問われるのは常に指導者であるオーベンであった。そのため、危機回避と自己保全の対策上オーベンはネーベンの患者についての理解度や行動に常に気を配らねばならなかった。
手術に入る機会はいやと言うほどあり、開頭術はアシスタントをしているうちに自然に流れが身に付いていた。しかし頭蓋内の手術手技については、当時鈴木先生が顕微鏡を使用していなかったため、第1と第2助手は手術に入っていながら如何に手術がすすんでいるのか皆目見当がつかないことも多かった。それというのも第一助手は左手で脳ベラを持って立っているため簡単に動くことができず、ときどき術者である鈴木先生が術野を覗かせてくださるのだが、手術操作中はとても頭蓋内を覗くことができなかった。顕微鏡を使用しないため(昭和62,3年ごろより顕微鏡を使用するようになった)、無影灯とスポットライトを使用していた。そのため常に術者の後に立ってスポットライトを入れる照明係が必要で、鈴木先生から常時厳しい注文をつけられるが、手術を観察するには最も良いポジションであった。これは主に助手以上のスタッフが担当していた。原則として専門医試験受験を控えた病棟チーフが第一助手を務め、手術所見を記載し術後症例検討会で黒板に描きながら説明しなければならなかったが、実際には第一助手は手術操作が見えていないため、手術経過を理解していない場合もあった。そこで鈴木先生が概略を教えてくださるのであるが、その他照明係から聞いたり想像しながらどうにか手術所見を完成させて、鈴木先生にご高閲いただいたくという、ビデオが普及している現在ではとても考えられない苦労があった。
さらに、大学としては当然であるが学会発表や論文執筆にとても力をいれており、一年目にもらった症例報告から始まり年1報が最低ラインであったように記憶している。中間オーベンとオーベンの2段階式指導体制により論文を往復し、最終的に教授に提出し最終校閲が終了し、投稿できる仕組みであった。研究経過については、毎週一回の研究検討会で教授をはじめ医局のスタッフ全員からご指導いただいた。病棟フリーで動物実験を行っている研究生は、毎週水曜日の朝5時半からの野球の練習の後、8時半からはじまる研究朝会で、鈴木先生に一週間分の実験データを提示し、説明しなければならなかった。一週間は新しいデータを出すにはあまりにも短く、週一回の研究朝会の必要性については疑問に思ったものであるが、今から振り返ると、週一回のプレゼンテーションに向けてデータが良く整理され、またありがち独善的なデータの解釈も客観的に評価されていたのだと感じている。何よりもこの研究朝会の刺激が研究推進の大きな原動力となっていた。学位取得の目的は世界初の医学的事象から新しい結論を帰納し社会に貢献することであるが、その研究過程を通じて科学的思考を身につけることも重要な目的である。大学院に入る、入らないにかかわらず、臨床期間と同じぐらい研究期間を与えられたので、ほぼ全員が専門医試験前に研究を終了しており、専門医試験勉強やその後の臨床おける科学的に思考過程が、早期に身に付いていたように思われる。一年間の研究成果と学会・論文発表については、忘年会の前日に行われる大研究朝会で審判された。医局員ならびに仙台市内に在職している全ての医師が集う中、全員の前で一年間の成果を発表し、鈴木先生より厳しいご指導をいただいた。容赦ない叱責に、医局員一同戦々恐々としていたが、まれに賞賛される者もいて、たいそううらやましく思い、来年こそはと誓うのであった。この大研究朝会は、夕食をはさんで7~8時間は要した。鈴木先生の忍耐力と教育にかける情熱には、今さらながら頭が下がる思いである。
現在の病院のinfrastructureや手術機器などのハード面もさることながら、初期臨床研修システムに代表される医師教育システムも、以前には想像だにできなかったほどに変化し、大学の研修ならびに研究システムも大きな分岐点にさしかかっている。常に脳神経外科の立場から、神経科学の発展を通じて社会に貢献することを第一と考えておられた鈴木先生のspiritを忘れずに、今後の脳神経外科の発展に少しでも貢献できればと願っている。

東北大学脳神経外科医局にて (後列左より2人目 筆者)