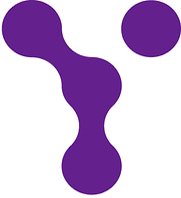「試験管が振れない医者は医者とはいえない。」
或る意味、大変挑発的な言葉であり、これを聞いて反感や一種の不快感を覚える方もいるであろう。出典は私が高校生の時に読んだ或る小説であり、作者が登場人物の医学部教授に語らせた言葉である。良い意味に解釈するならば、「医者というものは常に科学的根拠に基づいて職務を遂行すべき存在である」と換言する事が出来るが、ここに含まれたコノテーションには各人様々な受け取り方があると思われる。ただ、この言葉が当時漠然と医学に興味を抱いていた私の琴線に触れたことは間違いない。
この原稿の依頼を受けて私が何故現在歩んでいる道を選んだかを改めて考えてみると、月並みではあるが、そこには「書物」と「恩師」が大きく影響していることに気付いた。そこで、幾分予定調和的に成らざるを得ないが、これらをキーワードにしてこれ迄余り語って来なかった側面を中心に基礎医学者として発展途上の自分を記述したい。多くの蔵書を有した父の影響もあり、私は中学後半位からパスカル (Pascal, B.), デカルト (Descartes, R.), カント (Kant, I.) などに傾倒していた。これらを収録した岩波文庫の巻末に当時の同文庫に収録されていた著作の目録が付いており、その中にハーヴェイ (Harvey, W.) 著の『動物の心臓並びに血液の運動に関する解剖学的研究』という恐ろしく長いが魅力のある題名を持った本を見つけた。北海道の田舎の高校生であった私が早速書店に注文を出し、当時約1ヶ月という配本迄の期間を待ち遠しくしていた記憶が蘇ってくる。周知の様に、Harveyは血液循環の理論を既に17世紀に打ち立てた英国の解剖生理学者であるが、行間に溢れる緻密な観察の様子と精緻な実験計画に感銘した私は基礎医学の可能性をそこに見出した。
またよりその想いを強くさせたものとして、矢張り岩波書店から刊行されていた山村雄一の『病理生化学』という書籍が挙げられる。結核に依る肺の空洞形成メカニズムを実験免疫学的に解明した同氏は、 多数の英文論文に加え「実証的ではあるが、医学に関する一本の思索的な筋を通そうと努めた」と語るこの著作を発表していた。既に刊行後14年を経ていたが、未だ医学を学んでいない高校生にとっては大変新鮮な内容であり、そこに整然と並べられたストーリー性のある記述に魅せられた。従って、この本が独文や仏文、哲学、西洋史、更には政治学や分子生物学など興味の幅が広く進む学部を決めかねていた私の進路を決定した一冊である事に間違いはない。この本は正に「試験管を振る医者」の隠喩であった。
母校の旭川医大ではほぼ6年間哲学教室に通って、文科系学問への餓えも満たしていた。基礎医学と最初に実質的な接点を持ったのは、これより遅く医学科3年次の肉眼解剖学実習で出会った佐藤洋一助教授 (現在 岩手医大教授) に誘われて解剖学第一講座に出入りし始めた時であろう。当時、実質的に同教室の研究、教育を仕切っていた同先生から直接形態学の基礎的な考え方や手技を学び、また基礎医学研究室の雰囲気というものを体験した。 若く軽妙洒脱でありながらドイツ留学で培った重厚な学問的雰囲気を醸し出していた先生は、かなり生意気な医学生であった私を適当に往なし (鍛え?) ながらも、熱心に接して呉れた。この時に習得した基礎的知識や態度は、細胞生物学を専門とする様になった大学院から現在に至る迄一つのバックボーンとなっている。また、東大、本学を通じて研究室に出入りする数多くの学部学生と交流して来たが、これも同先生の影響に依るところが大きいのであろう。
さて、医学科2年次の頃から基礎医学の専攻を決めていた私は、『病理生化学』から始まったがんや免疫への興味が持続しており、この分野で伝統があり近場の北大第一病理学講座の大学院に進学しようと考えていた。丁度その頃、肉眼解剖学実習で後輩を苛めていた医学科4年の私を捕まえて、先生は「竹田君、tauとかMAP2という分子を知っている?」と訊かれた。 細胞骨格に関する知識がせいぜい微小管やアクチン繊維、中間径繊維に留まっていた当時の私には即答出来ず、 先生の「東大の廣川先生が最近やられている分子で、ホットな領域ですよ。」という説明に触発されて、早速図書館で文献を漁った。そしてそこに、従来の形態学にはないダイナミック手法を用いた細胞生物学という分野の将来性を見出し、この学際的な手法を習得すれば病理学や臨床医学を含む生命科学の全ての分野での研究に通用するという確信を得たのである。これが、現在の研究領域を決める契機になった事は言う迄もない。
かくして1992年、医学科卒業後直ちに東大医学部の廣川信隆教授 (解剖学第一講座) のもとに大学院生として入った私に最初に与えられたテーマは「遅い軸索輸送機構のcaged fluorescein photoactivation (ケージド化合物活性化蛍光消退法) に依る研究」というものであった。当時最新の解析手法を駆使してはいるが、大変基礎生物学的なテーマであり、どの様なモデル動物を使って、どの様に解析を行なうかを考えながらの正に試行錯誤的な研究であった。余り使用されていない実験動物 (アホロートル, axolotl) の脳の構造を調べる為に、学内或いは慶應や順天堂の図書館に通い1800年代後半のドイツ語の文献を探し求め勉強したり、ゼブラフィッシュ (zebrafish) の飼育法を習いに岡崎の基礎生物学研究所に行ったりした想い出がある。日本の細胞生物学のメッカと呼ばれる研究室にありながら、のんびりと100年以上も前の浩瀚な文献を読んでいられた背景には、現在よりも研究を取り巻く環境そのものにゆとりがあった事に加え、リベラルで自由放任主義の廣川教授の方針があったからであろう。 当時直接指導をして貰った岡部助手 (現在 東大教授) や、多くの優秀な先輩や仲間の中にあって現在の研究者としての基盤が形成された時期でもあった。
廣川教授のモットーは「高いスタンダードを設定し、かつ楽しく仕事をする」というもので、医学科の学生を含め当時既に40名を越えていたcritical massとも呼べる若い集団はこのスローガンのもと一種独特の熱気を帯びた雰囲気を放っていた。まだ研究室構成員の平均年齢が若かったこともあり、深夜12時になっても実験室には多くのひとが残っていた。この中から現在基礎、臨床を合わせて既に10名内外のPIが輩出され、全国、海外で活躍している。廣川先生の妥協を許さず、高いスタンダードのもとで目標を設定するという姿勢と、「人間には本能的に知りたいという欲望 (知識欲) があるのですよ」という基礎研究の本質的動機を体現した言葉は、今尚私が基礎研究を続けている源泉の一つになっている。
フランスに”Mouton de Panurge” (パニュルジュの羊) という言葉がある。 ラブレー(Rabelais, F.) の『パンタグリュエル物語』の中で、海に飛び込んだ先頭の羊の後を追って他の羊も全て海に飛び込んで死んでしまったという話に依拠した言葉であり、日本語の適当な諺を充てるならば「付和雷同」が一番しっくりと納まると考えられる。この逸話は現在の日本が置かれている様々な状況を語り分析する上で極めてシンボリックであると考えられる。 ここで敢えて解釈はしないが、 学生諸氏には臨床に進もうとも、或いは奇特にも基礎医学に進もうとも、自己責任で自らの判断をもって様々な情報や環境を吟味、選択し、そこに独自の進路を切り開く気概を持って貰いたいものである。

写真左:医学科6年次の臨床実習グループの仲間と(左から3人目が竹田、1991年、23歳) 写真右:文中のハーヴェイ『動物の心臓ならびに血液の運動に関する解剖学的研究』の表紙 岩波書店 1980