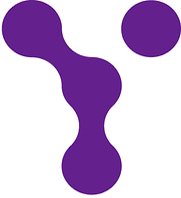子供の頃、乳歯のう蝕で近くの薄暗い木造2階の歯科医院に母親につれられ受診し、かなり高齢の先生に診てもらった記憶はあるが、永久歯に生え換わってからは一度も歯科に通っておらず、現在もう蝕はない。しかし漠然と歯科医師を目指し歯学部(歯学進学過程)へ入学し、無事に最短6年で卒業することができた。今となってはこの職業に就くことができてよかったと思っている。歯科の比較的細かい仕事が自分にあっていたのかもしれない。多分、読者のほとんどが医学部生、医学部出身者であろうと思われるので、若干異なる歯学部の、もう20年近く前になるが、当時の教育状況について思い出してみる。入学して2年間は、歯学に関する講義は一切なく、総合大学であったこともあり他の学部の学生と一緒になぜか、社会学、哲学、心理学などの選択講義と数学、化学、物理学、生物学、英語、ドイツ語などの必修科目があったと記憶している。この2年間は、何とも適当で、学業以外の事に充実できた、ある意味貴重な時間であったと思っている。あまり、出来のよくない私は、このまましばらく過ごせないかと都合よく思ってしまったこともあった。
最近では、さすがに医学、歯学の情報量の増大に伴い歯学に関連した講義が前倒しになっており、入学1年目から一応、歯科に関連した講義があるようだ。3年目になるとようやく歯学部の施設で講義、実習が行われた。入学前に抱いていた大学のイメージとは異なり詰め込み式の専門学校という感じであった。3年目から5年目までの間に基礎医学の他、内科、外科などの臨床医学の講義もあったが、やはり歯学独特の歯科保存学(う蝕治療、歯周病治療などを扱う)、補綴学(クラウン、ブリッジ、義歯などを扱う)、矯正学(歯並びの治療を扱う)、口腔外科学(抜歯、炎症、嚢胞、腫瘍などを扱う)など歯学部の講座が存在する分野の時間配分が多くとられていた。3年目から歯を削る実習が始まり、ここから手先が動く、動かないで大きく運命が左右した。歯学部に入学した学生は、医学部学生とは異なり、すべて歯科医師を目指すわけである。一般的に、開業歯科の先生を想像していただければわかりやすいと思うが、基本的に歯の治療は削って詰めることができなければならない。つまり、歯科は外科の一種であり、全員最低限この操作ができなければならない。当然、勉学に秀でていても手が動かないものもいる。これは努力によってある程度克服できるが、センスのあるないは卒後も大きく影響する。6年目には実際に、指導医のもと患者の歯科治療を行う。ある程度のノルマが課せられ基準を満たさなければ卒業できない。実習が多く、3年目から6年目まではよほどの事がない限り、欠席は許されない。試験も当時は筆記であり、ある科目一つで解答は答案用紙4枚ほどに至るものもあった。しかし、なぜか国家試験対策は全く行われなかった。今では、歯科医師国家試験はある意味選抜試験となっており合格率は70%を切るほどであるが、当時は国立大学歯学部の合格率は90%以上であり1カ月前から過去問をやり始めても十分間に合った。今の、国家試験受験者には同情するしかない。
さて、無事歯科医師となり、金沢大学医学部歯科口腔外科へ入局することとなり、ここから医学部での歯科医師生活が始まった。実はこの講座がどのような研究をしているか全くわからないままの入局であった。当時は、まず1年の臨床研修を行った後に2つの選択肢があった。さらに2年の臨床研修を行った後に退局するか、大学院に入学するかどちらかで、4年目以降大学院生でないものは自動的に大学を去ることになる。大学に残り仕事をするものは大学院を経て学位を取得することがこのころから当たり前になっていた。今となっては大学院大学とういう看板を背負った施設では当然のことと思われる。当時の山本悦秀教授は、口腔癌の浸潤様式を提唱した第一人者であったが、入局してしばらくしてからようやく研究内容がわかってきた。しかし、歯科口腔外科の多様性と将来性を考慮し、以前からこの医局で研究されてきた歯性感染症、山本先生の行ってきた口腔癌に加え、顎関節症、および顎変形症を研究テーマの4本柱として大学院生の研究テーマとした。1980年代に顎関節症が欧米で注目されはじめ、歯科疾患の中でもう蝕、歯周病(歯槽膿漏)に次いで非常に頻度が高く認められることから研究の必要性を迫られたものである。顎変形症も時代の流れで、外科手術による咬合治療を必要とする疾患であり顎骨全体を含めた究極の咬み合わせ治療として徐々に浸透してきていた。すぐに開業医勤務をするよりも大学で全身麻酔下での手術、病棟での全身管理などに興味を持ち始めたころで、同期の1人がなぜか大学院入学を早期に決断したので、便乗し軽い気持ちで入学することになった。いざ大学院生になってみると当然、4つの柱とは名ばかりでやはりこの教室での研究テーマの軸は口腔癌の浸潤様式に関する研究であることは間違いなかった。歯性感染症研究は歴代の研究がほぼ確立されており、研究器具も揃っていた。口腔癌研究は教授の専門分野として行われているので研究費も獲得しやすくマンパワーも豊富であった。しかし、顎関節症、顎変形症に関しては全国的に見ても新しい分野であり、まさに黎明期であったといっても過言ではない。顎関節症に関しては当時の上級医師が米国に留学し直接研究、治療法に関して学んで帰国し、かろうじて研究を遂行できるようになっていた。顎変形症ではすでに臨床が先行していたが、今振り返って考えてみると、ただこなすだけで精一杯であったように思える。私が、大学院生になった時すでに2年上の先生が顎変形症分野第1号の大学院生として在籍していた。しかし、新しい分野であり指導者がいないというありえない状態で、一切研究成果が得られていなかった。それどころか何ら具体的な研究ができず試行錯誤していた。顎変形症は癌などと違い放置しても死に至ることはない。実際に我々が治療にあたる多くの顎変形症患者は咬合不全、咀嚼障害、審美障害、顎関節症状を主訴とする主に顎骨と咬合のアンバランスを有しているが、細胞レベルでの異常はない。つまり、マクロ形態として人種、年齢、性別などを同一とした集団の中で各顎骨の計測項目が標準範囲外であるとするところで診断が決定する。顎顔面奇形を有する疾患において様々な遺伝学的な研究があり、われわれの扱う顎変形症に関しても同様な試みがなされている。しかし、そのような原因論に迫る研究は実際に当時の教室では不可能であり、癌研究の影響を多分に受けている上司の先生方の研究方法とは全く異なるアプローチが必要であった。臨床に直結した研究をしようと卒後間もない大学院生の2人は、指導者のいない状況下で何とか現存する実験器具でできることを模索した。ようやく、動物実験と数理学的解析を合わせた顎骨変形と顎関節構造の変化を検討した研究論文で1番目の大学院生は学位が取得できた。同様に、私もなんとか学位論文にまでこぎつけ学位取得に至った。その後、顎変形症の分野での大学院生は、大学院修了後間もない私の指導のもと、海外からの留学生も含め7人の学位取得者を輩出できた。研究テーマは顎変形症臨床を意識したもので、生体材料、力学的刺激を応用した顎骨再生に関する研究、顎変形症と顎関節症発症に関する形態および力学解析、口腔外科手術における三叉神経知覚誘発電位および神経組織変化に関する研究を主として行ってきた。現在も、ここ山梨大学で継続して新たな大学院生とともに研究を継続している。
なんとか現在まで、大学に居座っているが、大学の非常な雇用体制は私にとって大きな障害であったことを述べたい。大学院修了後、一時、米国に留学し帰国したが身分は医員であり40歳直前までいわゆる日雇いであった。最初の私の指導した大学院生4人目までは医員の身分でなぜか指導していたわけである。理不尽な状態と思いながらも、自分の臨床、研究、考え方に共感してこの分野で研究したいと思って入学した大学院生に対し、本来私は指導する立場にないからと突き放すわけにもいかず、学位取得まで到達させた。当然、医員の状況ではアルバイトをしなければ生活費は稼げなかったが、基礎の先生に比べればまだましであろうとなんとかやってきた。しかし、今となっては条件が悪いながらも大学院生に対し指導することで自分も成長できたと感謝している。ちなみに、大学院生時代はもちろん無給で、大学病院での外来、病棟業務を行いながらの研究であり、収入はアルバイトだけであった。実はこのような待遇の者が数人おり私からすると能力もありそこそこの実績のあるものもいたがが、やはり年齢と生活の事を考えて医局を去って行った。いわゆるポスト不足による中間層の希薄化が生じ、将来性に希望を持てない若い世代が比較的早期に大学を去って行った。大学以外にも全国的にもそのような施設は多いと聞く。それを考えると、現在の大学院生は、同時に医員待遇にもなれ収入面では非常に恵まれていると思う。しかしながら、大学院への進学希望者が少ないのは非常に寂しい気がする。確かに、将来的に大学に残れる人数には限界があるが、研究に従事することはその後の臨床に大きく影響を及ぼすものと思っている。私も、当時大学院に入学する時に考えたことは、卒後の大事な時期に技術の習得が大学院に入学してもできるのかということであった。しかし、臨床講座であればやはり臨床に関連した研究に重点を置くわけで全く異なることをしているわけではない。臨床と研究は非常に密接に関連していて切り離せないものであるという事が、実際に大学院に入学し研究に従事するようになって始めて認識できた。非常に些細な治療技術もそれを客観的に評価できて、さらなる技術が生まれるのである。つまり、その評価、検討がそのまま研究であり、さらなる研究の足がかりになるのである。臨床に携わる者は、遠い将来に役に立つだろう研究と同時に、目の前の患者に対し既存の知識、技術を駆使して対応していくための研究も必要なのである。
医学生が医師になり、まず大学に残るか、また大学に残り研究をする上でもやはり臨床と研究のどちらに重点を置くべきか迷う時期があると思われる。しかし、研究は臨床においてあらゆる状況で関連してくるものであり、なにも実験室で行われることだけが研究ではない。臨床に直結した研究もあれば基礎的な研究もある。私は歯科口腔外科臨床に関連した研究しかできていないが、歯科医師のidentity をできるだけ示せる研究をしたいと考え実行している。自分の行っている研究はImpact Factor重視の時代において価値は低く、高尚な研究ではないかもしれないが、実際に患者数も多く、専門性という意味では重要な分野であると思っている。
私は縁があって山梨大学医学部歯科口腔外科に赴任することになったが、山梨大学に関わったすべての者がここに誇りを持てるようになれば、人は集まり、この山梨大学から多くの質の高い研究成果が得られると思われるものと信じている。

国際学会での再会 (左が筆者、右が金沢大学で学位を取得したバングラデッシュ出身の先生。)