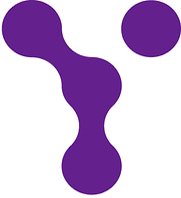私は、国境の島、長崎県は対馬に生まれました。中学まで過ごした彼の地で、将来は地域医療に従事したいと希望を抱き、内地福岡の高校に進学しました。その後、鹿児島大学医学部を卒業し、大阪大学、カン研究所(京都)、富山大学(旧富山医科薬科大学)と流れに流れて、昨年4月に本学医学部生化学教室に着任しました。
私が臨床医学(地域医療)ではなく、基礎医学の道に進むことになったのは一冊の本がきっかけです。それは、ブルーバックスの「遺伝子が語る生命像」(本庶佑著)でした。高校時代、物理化学選択だった私にとって、本書の内容は至極新鮮に映りましたし、本庶先生の学問への姿勢に大いに憧れたからです。当時はもちろんe-mailなどありませんでしたので、私はすぐに京都大学医学部の本庶先生に電話をかけ(今思うと若気の至りです)、“先生の本を読んで分子生物学に興味をもったので夏休みに実験させてほしい”と願い出ました。“来たまえ”とお返事いただいたときのことは昨日のことのように思い出せます。夏の1ヶ月、当時大学院の2年生だった古川貴久先生(現大阪バイオサイエンス研究所部長)について分子生物学のイロハを教わりました。当時はキャピラリーシークエンサーなどもなく、X線フィルム上のATGCのバンドを古川先生が読み上げ、それを私がノートに書き写していくこともやりました。古き良き時代でした。本庶研では、朝起きて、喫茶店で古川先生と一緒にモーニングを食べ、夜は近所のみゆき湯で汗を流して、またラボに戻る日々でした。ラボで交わされる会話のほとんどは暗号にしか聞こえませんでしたが、それでも、世界最先端のラボに身を置いて、皆が“サイエンスにハマった”環境で、実験できることがなんとも言えない心地よさでした。必然、自分も基礎医学の道に進んで世界のひのき舞台で活躍したいと思うようになりました。翌年は、本庶先生に推薦書を書いて頂きMITのHarvey Lodish教授のもとでsummer studentとしてひと夏を過ごしました。当時、Lodish研には鹿児島大学医学部の腫瘍研究施設助教授の吉村昭彦先生(現慶応大学医学部教授)が留学されていました。失敗ばかりでよく怒られました。今でも頭が上がりません。その後卒業までは、鹿児島大学で放課後、基礎医学の講座に出入りして実験をやっていました。臨床講義やポリクリも始まると、さすがに臨床もいいなあと思ったりもしましたが、やはり基礎に進みたいとの思いが強く、現実問題としてどの大学院に進学するか悩む日々が始まりました。
転機は6年生になったばかりの春に突然やってきました。当時出入りしていた臨床検査医学講座の丸山征郎教授に声をかけられ、publication listを渡されました。
「来週、セミナーで神戸の高井さん呼んでるから、話聞いてみたらいいよ。これはpublication listね。大学院生探してるみたいよ」
時効だから言いますが、当時の私は高井義美先生を知りませんでした。誰それ?って感じで、渡されたpublication listを読んで驚愕しました。Journal of Biological Chemistryに年間10報以上コンスタントにpublishしているではありませんか。多いときには20報近くありました。翌週、高井先生に初めてお会いし、“うちに来たらなんでも好きなことできますよ。”とフランクに関西弁で誘っていただき、“なんて気さくな方なんだろう”と感動さえ覚えました(笑)。最終的には当時高井研の助教授だった貝淵弘三先生(現名古屋大学医学部教授)と黒田真也先生(現東京大学工学部教授)に詳しいお話を伺って、高井研に行くことを決めました。
高井研では、当時も多くの大学院生がいて切磋琢磨していました。いわゆる“しんどい”ラボでしたが、先輩たちが次々に教授になっていくのを見ていると、自分もいつかはなれるのかなと自然と考えるようになりました。もちろん、先輩たちがやってきたハードワークとそれに見合う業績を出す必要がありましたが。サイエンスの世界では、研究(実験)に最大限の時間と労力を割ける時期は限られています。それはおそらく大学院時代とそれに続くポスドク時代ではないかと思います。この時期に確固たる研究スタイルや願わくば“きらりと光る仕事”を出す必要があるのでしょう。“サイエンスにハマる”時期がどうしても必要なのだと思います。実験がうまくいかなくて気分転換に映画を観に行っても、全然面白くない。かといって、実験がうまく行って出かけても、次の実験が気になってやっぱり面白くない。とにかく、すべてはサイエンスのためにという時期が必要なのです。私にとっては高井研で過ごした日々がまさにそういう時代でした。当時は、“しんどい、しんどい、あーしんどい”と思っていましたが、そんな時期があってこそ、その後の試練を乗り切れるのだと思います。
私にとっての最初の大きな試練はカン研究所での5年でした。右も左もわからぬままグループリーダーになり、テーマもゼロからのスタートでした。私たちが見出した新規分子が欧米との競争になってしまい、特に最初の論文が出るまでの2年半は大変胃の痛い毎日でした。相手がアメリカのビックラボだったこともあり、“向こうはもう論文を投稿しただろうか。NatureやNeuronに出してくるだろうか”と焦る毎日でした。2002年の夏に論文が出てからも、競争はさらに激しくなって、いつ先を越されるか不安な日々が続きました。そんな状況でも、“しぶとく粘って最後まであきらめない”姿勢で競争に勝ち、いくつかの重要な成果と論文を世に送り出すことができました。好きこそものの上手なれとは言いますが、好きでやっていることでもしんどくてうまくいかないときは必ずあります。そこで、踏ん張って先へ進めるかどうかが大事になってくるのでしょう。
現在、医学部でもとりわけ基礎医学を志望する学生は減っています。ポスドクの不安定な雇用形態や、アカデミックポストの減少などもあり研究そのものを志向する学生も全般的に減少している昨今です。若手が希望を持ちながら研究にまい進できるような環境・体制の整備は、また別の次元の問題ですが、それでもやはりサイエンスは面白いです。一度ハマったらなかなか抜け出せません。ときに競争は激しくなりますが、世界の研究者と交流し、自らの世界観を広げることができるのもサイエンスの醍醐味の一つです。
そこのあなた、私たちと一緒にサイエンスにハマってみませんか?

中央、白のTシャツが筆者。大学院1年目の激しく暑かった夏。