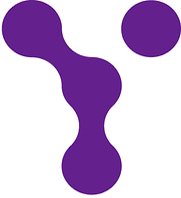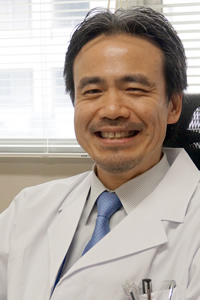もとより医師を志してきたわけではない。親父が土建業を営んでいたこともあり、何となく工学系の大学に行って、その後は親父と似た仕事に就くのだろうというおぼろげながらも自分なりの将来像を抱いていた。高校3年の秋に入り、担任教師が怪我をし、翌週の授業で『人が死を恐れる限り、医師は強い職業』という旨の話があった。その後、私が幼少時に亡くなった実母が私を医師にしたがっていた、との話を親父から聞き、私の心は決まった。大学時代は、医学部なりの実習の忙しさはあったが、昼間はラグビー、夜は友人との麻雀に明け暮れ、特に将来に対する準備をしてきたわけではない。今とは違い、当時は、卒業時点で将来の専門分野を決める必要があり、5回生の冬頃から自らの就職先とも言える進路選択に悩んだ。最初は循環器内科へ進もうと考えていたが、親友から『お前は内科的な思考をする傾向にあるので、外科系に行くべき』との助言を受けた。いずれ訪れる医師過剰時代には目立つことが重要、自らが持つ本来の特性以外の診療科を目指すと良いとの趣旨である。今から考えれば極端な考えではあるが、その助言に従い外科系に進むことにした。最後は消化器外科と耳鼻咽喉科との選択に悩んだが、医師を志した際に恩師に言われた言葉を思い浮かべ、『命』に直結する機会が多い母校の消化器外科・乳腺外科教室の門戸を叩いた。
研修医時代は、大学病院で上司の先生方の多数の手術に参加したが、今日のような鏡視下手術は無い時代である。全く見えない術野に対し、心眼で見ながら術野に被さる臓器を牽引して手術の介助をした。市中病院に専攻医として赴任してからは、連日が手術の日々であった。明けても暮れても手術三昧であり、卒後直ぐに結婚した家庭は全て妻任せであった。外科医の宿命であるが、家族との予定のドタキャンは日常茶飯事、ディズニーランドへの家族旅行を当日に予定変更し、妻と子供だけ行かせたこともある。そんな中、5年目で大学病院に戻ることになり、大学院に入学するか否かの選択に迫られた。元より強い志で医師になったわけでもなかったが、その当時読んだ東京大学名誉教授石本巳四雄著『科学への道』の中で、著者らが研究を知的遊戯ととらえていたのに影響を受け、時間を忘れて没頭する者がいるという研究というものを、自らも一度経験してみたくなった。今から考えても後にも先にも自ら能動的に進路を決めたのは人生でこの一度だけのように思う。それからは、当時二人目を身籠っていた妻に大学院進学の説得の日々であった。結婚した夫が、一旦社会人になった後、再度学生になるということが受け入れ難かったようで、この説得には時間を要した。結果、私自身の当時の毎月の小遣いを半額にすること、土曜日曜はアルバイトをして多少のお給料は稼ぐことを条件に、妻も渋々承諾した。
それからの2年間は、大学病院での臨床も行いながらの研究生活が始まった。最初に与えられた課題は、当時、教室で行っていた『直腸癌に対する化学・放射線・温熱の三者併用療法の長期成績についての検討』であった。電子カルテの無い時代である。古いカルテを調べるため、かび臭いカルテ庫に入り、夜な夜な実際の治療歴や術後経過を各々の患者について調べていった。予後がわからない患者さんには直接ご自宅にお電話して消息を確認することもあった。結果、ある程度の局所制御効果はあるものの、不思議なことに遠隔転移が対照群に比較してやや多い結果であった。論文化するように、との上司から指示のもと、関連論文を多数熟読したが、知らないままに気付けば教室内で私自身が最も詳しくなっていた。それが面白かった。ただ、遠隔転移が増える可能性については、現在はある程度、その可能性は示唆されているものの、当時、記載された論文は殆どなく、あまり強調して論文には記載しなかった。また当時、後輩と検討した別の解析で、大腸癌の臨床病理学的因子の時代的変遷について調べていた際、少しずつ高分化型腺癌が減少傾向にあり、中分化型腺癌が僅かながら増加傾向にあるとの結果を得た。関西風に言うと『そんなアホな』である。当時の上司にそのまま報告したが、学会ではその点は強調せずにサラッと報告することにしたが、学会会場で他施設からの発表を見て驚いた。殆ど全ての施設で同様に中分化型腺癌が微増しているとの結果であった。当時の重鎮達の考察では、内視鏡治療の普及により高分化型腺癌の芽となる腺腫や小さい癌が多数治療を受けているためであろう、とのことで、これには、自分達が得た結果をそのまま自信を持って報告しなかったことを後輩と共に悔やんだ。その後、本格的に大学院生としてのBenchでの研究生活を送ることになり、『分子生物学的手法による解析の外科診療への応用』という、実に大きい(?)また大雑把なテーマを当時の教授からいただいた。詳細なテーマは与えられず、『とりあえずやってみなはれ』という事である。ただ、師がいないと出来ないテーマであり、科研費のテーマや医育機関名簿の専門領域などを見て、自らの師を探した。結果、灯台元暗しで、当時、京都府立医大の衛生学教室に蛍光ハイブリダイゼーション法(FISH法)の日本の先駆者である稲澤譲治先生(当時講師、現在、東京医科歯科大学教授)がおられることに気付き、上司と共にお願いにあがった。快く受け入れていただき、テーマの相談から始まった。稲澤先生が元臨床医であったこともあり、臨床に即した研究という、私の希望も聞き入れていただき、乳腺疾患に対するFISH法の応用というテーマで研究を開始した。現在では当たり前となった臨床サンプルの間期核(分裂期でない核)上での染色体の数的異常の検出である。幸いにも、乳腺疾患の中で乳癌細胞は染色体の数的異常が多い癌であり、針生検による細胞診サンプルで次々と染色体異常の検出が可能であった。上司の指示に従って急いで論文化したが、英語が苦手な自分と世界中の著名な先生方が、一つの論文を通してDiscussionし、より良い論文に仕上げるという、これが楽しかった。研究を行う一方で、通常任務として外科臨床も担当していたが、その中で多臓器に多数の癌の発生を認めた患者さんに遭遇した。極めて珍しかったため、同僚とは、ご家族に毒を盛られているのでは、との要らぬ詮索をしたりもした。もしかしたらと思い、これまでの報告を調べてみると、大腸癌の中にポリポーシスを示さないものの他臓器に癌が合併するという新たな疾患群が提唱され出していた。研究の上司である稲澤教授にも相談し、その解析手法について詳しい先生を紹介していただき、早速パラフィン切片からDNAを抽出し解析にかかった。パラフィン切片の中に含まれている情報を掘り起こして正解を見出す、これまた楽しかった。結果、サスペンスを読みすぎる同僚との予想は覆され、多臓器多発癌の素因が見つかりサイエンスで話がついた。
研究に没頭していたある日、自宅に帰ると妻から『あんた、アメリカ行くん?私は嫌やで』と急に言われた。初耳であったが、当時の外科教室の上司が知り合いの米国ワシントン大学のProfessor Hakomoriに私のことを相談してくださったようで、急に自宅に電話がかかってきたようである。内容は、『いつ来れるか?』であった。上司に聞きに伺ったところ、大学院生活を早く終えるか、もしくは留学をするか、という二者択一だった。これには自分自身も悩んだ。先に述べたように英語は大の苦手である。ただ、人生一度切りであり、留学を終えてからの自らを想像し、異国を見るのも悪くないと考え留学してみることにした。それからは再度、妻の説得の日々であった。これには時間を要した。外科修練を積むために京都市外の病院へ勤務した際にも都落ちと考えた生粋の京女であったが、最終的には留学に息子達も連れて同行してくれた。
米国での研究生活が始まったが、私の留学先はABO型の血液型を決定する遺伝子をクローニングしたラボであった。血液型は細胞表面に付いた糖鎖によって決まり、人の細胞には血液細胞以外にも同様の表面抗原が発現しているとのことであった。調べてみると、それら上皮細胞上にも発現している血液型抗原が癌化と共に変化することが多く、それら変化する血液型抗原によって癌患者の予後に違いを認めるとの報告もされていた。そこで一見、無謀にも思えるが、癌細胞の血液型抗原を遺伝子導入によって強制的に変化した際にどのような癌形質の変化を認めるか、という疑問がわいてきた。当時、研究所の上司や同僚は考えない試みであったが、結果は驚くことに遺伝子導入による血液型糖鎖抗原の発現変化によって癌細胞の浸潤能が変化した。血液型糖鎖抗原が主に付着している蛋白を検索してみるとインテグリンという浸潤能に関与している分子に多く付着していることも判明した。その研究結果を、上司であるProfessor Hakomoriに持って行ったところ、言われたのが『サイエンスは小説より奇なり』の一言であった。その後は延々と教授室で研究に対する心掛けや苦労話をお聞きしたが、『自らが持つ知見を基にメカニズムや結果の推察を行い研究のテーマ―を考えるが、予想通りの結果が出ても実は新たな事は何も無い。予想に反する結果が何度となしに出たとき、その中に新知見が含まれるものだ』とのことであった。考えないのも駄目だが、考え過ぎてもだめ、とりあえずやってみなはれ、ということであろう。また、出た結果については、それを先入観無しに真摯に受け止めて、その内容と結果を吟味し、深く考察をしなさい、とのことであった。
以来、消化器外科医として診療に携わる一方で、大学院生の先生方とは『基礎研究によって得られた知見の臨床応用』、また、臨床研究においては『実臨床におけるClinical questionを元にした研究』という、二つの大きなアイデアのもと研究を続けてきた。私自身が手を動かして研究していた時代から、新たな知見を得た際には大きな喜びを感じ、『もしかしたらこの知見を知っているのは自分だけかも』と思うような場面にも何度か遭遇した。もちろん、その時にも大きな喜びはあるが、論文化が進み論文掲載が決定した際にも別の喜びがあり、また、他の研究者に自らの論文が引用された際には更に新たな喜びを感じる。まさに知的遊戯である。現在、縁あって山梨大学に赴任し、医局の後輩達と一緒に研究を開始した。後輩達との前述したような研究における知的遊戯ほど楽しいものは無いと感じる今日この頃であり、若い先生方には、是非この知的遊戯の世界に一度は足を踏み入れて欲しく思う。