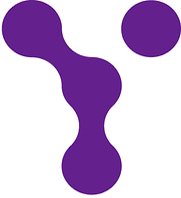「現在、卒後臨床研修制度以降、臨床重視、研究軽視の風潮があるのは極めて残念である。“研究”なくして大学病院の存在意義はないものと考える。」
病院長就任以来、常にこのようにコメントしているが、私が研究をはじめた“きっかけ”はそんな大それた思想に基づいたものではなかった。ある意味“人とのきずな”でたまたま東京大学皮膚科に入局した。当時の教授が野球好き(私は中学~大学まで野球部)でゴルフ部部長(大学ではゴルフ部にも所属)で、医局員も野球部の先輩が多く、積極的に勧誘されたからである。当時マイナー系の科は、皮膚科も例外でなく診療、研究ともほとんど何をやっているかわからず全く学生に人気がなかった。入局してみると思ったとおり大学院もなく、“研究”の環境はなかった。入局1年目、進行期メラノーマの患者さんをいきなり2名受け持たされた。1人はアンプタ、1人は耳を全切除と大手術となったが、いずれも転移で亡くなってしまった。当時(今も)化学療法、放射線療法も効果は極めて限定的であった。免疫療法もBCGや丸山ワクチンぐらいしかなく、いずれも科学的にみると効果はなかった。ただ何とかしたいと思う思いだけは募った。そこで独学で“がん”の勉強をしたり新しい治療法を学ぶべく日本癌学会に入会した。そこで出会った東大や国立がんセンターの脳外科医に細胞培養法、flow cytometryなどの研究の手ほどきを受けた。ラッキーなことにその論文で最年少で日本皮膚科学会皆見賞(the best paper of the year)を受賞してしまった。(Bedside to Bench)ただ実際の臨床には残念ながら全く役立たなかった。将来のがん治療は免疫療法しかないと考え、免疫学教室 多田富雄教授の門をたたき、免疫の基礎を学んだ。実際、免疫学を学んでみると奥が深く、簡単にはがんを治せないことがわかり、長い道のりが必要と考えるようになった。
ちょうど、その頃米国NIHでの留学話が持ち上がり、皮膚の免疫を本格的に学ぶ機会に恵まれた。NIHでは基礎的な皮膚免疫学の研究に打ち込み一定の成果を上げることができた。“研究”そのものも奥が深く、新しい発見に知的興奮が得られるのも面白い、と考えが変わっていったのも事実である。さらに帰国後、自分自身の研究も重要であるが当時の欧米からかなり遅れていた日本の皮膚科学研究にも危機感を持ち、志を同じくする同士達(当初は全て東大出身ではなかった)と日本研究皮膚科学会(JSID)のなかで積極的に活動した。これが評価されJSIDの事務総長(2002-2005)、理事長(2005-2008)となり、2008年、国際研究皮膚科学会(IID)会長をつとめることにつながった。IIDでは日本からの演題がヨーロッパ全体よりも高く評価され、大変嬉しく思ったのも記憶に新しい。
現在、われわれの教室の2大テーマは柴垣准教授、猪爪医局長率いる“がんの免疫療法”(
Bench to Bedsideを目指している)と川村講師率いる“皮膚免疫ならびにHIV感染”であるがそれぞれが世界的な業績を上げている。IIDの成功も彼らをはじめとする教室員の努力の賜物と感謝している。今後もBedside to Bench, Bench to Bedsideの双方向の研究を続けていけたらと考えている。

NIH時代、“野球”で活躍し、ラボの皆から認められた。(1983年)(2列目右より2番目)